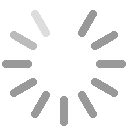000
Gグループ⑤-7
+本文表示
一応スレたてとこ\(^^)/
026
料ノ賦課ニ関スル事件、租税滞納処分ニ関スル事件、営業免許ノ拒否又ハ取消ニ関スル事件」等、列記主義の原則により不服申立てのできる場合を限定的に規定していたこともあり、この法律によって十分な救済が図られる内容とは言い難かった。
また、日本国憲法第76条2項後段は行政機関が終審を行うことを禁止しているが、反対解釈すれば前審を禁じてはおらず、裁判所法3条2項も行
027
1962年(昭和37年)制定の行政不服審査法(以下「旧法」という。)制定以来、長らく実質的な改正はなかったが、2014年(平成26年)に現行法を抜本的に改正した行政不服審査法(平成26年6月13日法律第68号)が公布され、2016年(平成28年)4月1日に施行された(平成27年11月26日政令第390号)[1]。
028
(1)審査請求への原則一元化
旧法での基本的な不服申立類型は、審査請求、異議申立ての2種類であった。審査請求を経るか、異議申立てを経るかは原則、該当する処分に関して処分庁に対する上級行政庁があるかないかにより区別されていたものの、異議申立ては審査請求と比較して簡略な手続きであり、かつ処分庁自らが決定庁となり決定を下すような状況となることが大半となり、自ら下した処分を自ら過ちであると認めた上で処分庁が処分を取り消すかまたは変更するようなことが異議申立者にとっては容易に期待できない面があった。
このため、異議申立てについては、適正手続の保障の観点から問題が残った。
さらに上級行政庁が偶然存在するか否かにより、手続保障に差異が生じることや、本来異議申立てとなるべきものを不服申立者が単純に勘違いして審査請求としてしまったり、逆に審査請求となるべきものを誤って異議申立てとしてしまったりしたために、その補正の結果、申立て可能な期間を経過してしまい、結局不服申立てができなくなるのを招きやすい等という問題も残った。
これらの問題を克服し、適正手続の保障・促進の観点から、審査請求への一本化が図られた。
029
(1)審査請求への原則一元化
旧法での基本的な不服申立類型は、審査請求、異議申立ての2種類であった。審査請求を経るか、異議申立てを経るかは原則、該当する処分に関して処分庁に対する上級行政庁があるかないかにより区別されていたものの、異議申立ては審査請求と比較して簡略な手続きであり、かつ処分庁自らが決定庁となり決定を下すような状況となることが大半となり、自ら下した処分を自ら過ちであると認めた上で処分庁が処分を取り消すかまたは変更するようなことが異議申立者にとっては容易に期待できない面があった。
このため、異議申立てについては、適正手続の保障の観点から問題が残った。
さらに上級行政庁が偶然存在するか否かにより、手続保障に差異が生じることや、本来異議申立てとなるべきものを不服申立者が単純に勘違いして審査請求としてしまったり、逆に審査請求となるべきものを誤って異議申立てとしてしまったりしたために、その補正の結果、申立て可能な期間を経過してしまい、結局不服申立てができなくなるのを招きやすい等という問題も残った。
これらの問題を克服し、適正手続の保障・促進の観点から、審査請求への一本化が図られた
030
(1)審査請求への原則一元化
旧法での基本的な不服申立類型は、審査請求、異議申立ての2種類であった。審査請求を経るか、異議申立てを経るかは原則、該当する処分に関して処分庁に対する上級行政庁があるかないかにより区別されていたものの、異議申立ては審査請求と比較して簡略な手続きであり、かつ処分庁自らが決定庁となり決定を下すような状況となることが大半となり、自ら下した処分を自ら過ちであると認めた上で処分庁が処分を取り消すかまたは変更するようなことが異議申立者にとっては容易に期待できない面があった。
このため、異議申立てについては、適正手続の保障の観点から問題が残った。
さらに上級行政庁が偶然存在するか否かにより、手続保障に差異が生じることや、本来異議申立てとなるべきものを不服申立者が単純に勘違いして審査請求としてしまったり、逆に審査請求となるべきものを誤って異議申立てとしてしまったりしたために、その補正の結果、申立て可能な期間を経過してしまい、結局不服申立てができなくなるのを招きやすい等という問題も残った。
これらの問題を克服し、適正手続の保障・促進の観点から、審査請求への一本化が図られ
031
(1)審査請求への原則一元化
旧法での基本的な不服申立類型は、審査請求、異議申立ての2種類であった。審査請求を経るか、異議申立てを経るかは原則、該当する処分に関して処分庁に対する上級行政庁があるかないかにより区別されていたものの、異議申立ては審査請求と比較して簡略な手続きであり、かつ処分庁自らが決定庁となり決定を下すような状況となることが大半となり、自ら下した処分を自ら過ちであると認めた上で処分庁が処分を取り消すかまたは変更するようなことが異議申立者にとっては容易に期待できない面があった。
このため、異議申立てについては、適正手続の保障の観点から問題が残った。
さらに上級行政庁が偶然存在するか否かにより、手続保障に差異が生じることや、本来異議申立てとなるべきものを不服申立者が単純に勘違いして審査請求としてしまったり、逆に審査請求となるべきものを誤って異議申立てとしてしまったりしたために、その補正の結果、申立て可能な期間を経過してしまい、結局不服申立てができなくなるのを招きやすい等という問題も残った。
これらの問題を克服し、適正手続の保障・促進の観点から、審査請求への一本化が図
032
(1)審査請求への原則一元化
旧法での基本的な不服申立類型は、審査請求、異議申立ての2種類であった。審査請求を経るか、異議申立てを経るかは原則、該当する処分に関して処分庁に対する上級行政庁があるかないかにより区別されていたものの、異議申立ては審査請求と比較して簡略な手続きであり、かつ処分庁自らが決定庁となり決定を下すような状況となることが大半となり、自ら下した処分を自ら過ちであると認めた上で処分庁が処分を取り消すかまたは変更するようなことが異議申立者にとっては容易に期待できない面があった。
このため、異議申立てについては、適正手続の保障の観点から問題が残った。
さらに上級行政庁が偶然存在するか否かにより、手続保障に差異が生じることや、本来異議申立てとなるべきものを不服申立者が単純に勘違いして審査請求としてしまったり、逆に審査請求となるべきものを誤って異議申立てとしてしまったりしたために、その補正の結果、申立て可能な期間を経過してしまい、結局不服申立てができなくなるのを招きやすい等という問題も残った。
これらの問題を克服し、適正手続の保障・促進の観点から、審査請求への一本化が図られた。
033
(1)審査請求への原則一元化
旧法での基本的な不服申立類型は、審査請求、異議申立ての2種類であった。審査請求を経るか、異議申立てを経るかは原則、該当する処分に関して処分庁に対する上級行政庁があるかないかにより区別されていたものの、異議申立ては審査請求と比較して簡略な手続きであり、かつ処分庁自らが決定庁となり決定を下すような状況となることが大半となり、自ら下した処分を自ら過ちであると認めた上で処分庁が処分を取り消すかまたは変更するようなことが異議申立者にとっては容易に期待できない面があった。
このため、異議申立てについては、適正手続の保障の観点から問題が残った。
さらに上級行政庁が偶然存在するか否かにより、手続保障に差異が生じることや、本来異議申立てとなるべきものを不服申立者が単純に勘違いして審査請求としてしまったり、逆に審査請求となるべきものを誤って異議申立てとしてまったりしたために、その補正の結果、申立て可能な期間を経過してしまい、結局不服申立てができなくなるのを招きやすい等という問題も残った。
これらの問題を克服し、適正手続の保障・促進の観点から、審査請求への一本化が図られた。
034
xxxxxxxxxxxxxxxxx
035
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
※このスレッドのコメントはこれ以上投稿できません。